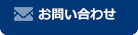― 贈ることば ―
学士課程を了えられた皆さん、ご卒業おめでとうございます。また、修士課程を了えられた皆さん、ご修了おめでとうございます。今日ここに、皆さんは、めでたく学士、あるいは修士となられました。心よりお祝いを申し上げます。
さて、お手元に、本日の式次第とともに、レモン色の紙があるのがわかるでしょうか?それは、皆さん一人ひとりに贈る詩です。タイトルはLeave。これまでも皆さんの先輩方に渡してきました。
皆さんは折にふれ、「こまつから、未来へ」という、本学のキャッチコピーを目にしたことがあると思います。出典は、じつは、この詩でした。卒業、修了ののち、ある人は小松を離れ、ある人は小松に残ります、けれども...、というのが、全6節中の第4節です。この節最後の行で、No. のあと、Everyone is leaving for the future! とつづきます。誰もが、未来へと、旅立つわけです。
未来は、しかし、日々同じではありません。科学技術の進歩は日進月歩。世界情勢も刻々変わります。皆さんはこれから、社会人として、さまざまな変化に対応し、そう遠くない将来には、中堅、あるいは指導者として、職場・組織をリードしてゆかねばなりません。
では、目まぐるしい変化に一体どう対応していったらよいか?皆さんの巣立ちにあたり、わずかな経験を語り、少しでもご参考になれば、と思います。
わたしは、3年ほど臨床医をやったあと、基礎医学研究の道に入りました。1970年代後半のことです。当時、分子生物学が、原核生物からヒトを含む真核生物へと研究対象をひろげようとしていました。遺伝子をクローニングしたり、DNAの塩基配列を決定することが可能になりつつあり、関連する技術の進歩はまさに、日進月歩でした。
医学の分野でしたが、いちばん支えになったのは、物理、化学といった基礎科学でした。わからなければ基礎に立ち返って考える、あるいは踏み台にできる基礎をもつ、すると、どんな進歩にも着いていけるように思えました。
皆さんにまず言いたいのは、基礎をおろそかにせず、学びを怠らないことです。わたしの恩師は、「永遠の素人たれ」と教えました。どんな発明、発見や論文発表も、なしえた瞬間、過去の栄光となり、新たな挑戦をはじめなければ、前途は無です。その度、新しい勉強、新しい基礎づくりが必要になるわけです。皆さんが進む分野によっては、基礎は足元ばかりでなく、雲の上にもあるでしょう。クラウドの時代が到来しています。たとえば、米国ではすでに、政府の指示でGoogle、Microsoft、Amazon3社の共同によって、クラウドネイティブというプラットフォームが形成されており、あらゆる病院の医療情報が全米共通のシステムで閲覧可能になっています。クラウドネイティブによって、情報犯罪も、未然にガードされています。
以上のような、進路により多様性のある、専門上の基礎に加え、universalに共通しうる基礎もあります。
それは、心構えのうえでの基礎、あるいは哲学、思想と言っていいかもしれません。たとえば、トルストイ『戦争と平和』の主人公、ピョートル・キリールイチ・べズーホフを例にとりますと、かれはよく彷徨います。しばしばピストルを手にして。あるときは決闘のあと雪原で。あるときは廃墟となったモスクワで。ナポレオンの暗殺も企てます。べズーホフ伯爵は、対人関係のうえでも、よくゆれうごきました。が、フランス軍の捕虜となり、「石のように寝て、まるいパンのように起きる」プラトン・カラターエフという素朴に生きる農民に出会って以降、べズーホフのあり方は一変し、安定した率直な生き方をするようになります。
はたらくことは大切です。が、本を読んだり、考えたりすることも大切です。これからの人生航路を生きぬいて行くうえで、よすがとなるような原点が、皆さんのうちに打ち立てられるよう、念願してやみません。
司馬遷は、「故に往時を述べ、来者を思う」と言いました。「来者」とは、やがて来たる、未来の人、との意味です。以上、いささかの往時も述べ、来者たる皆さんに贈ることばといたします。